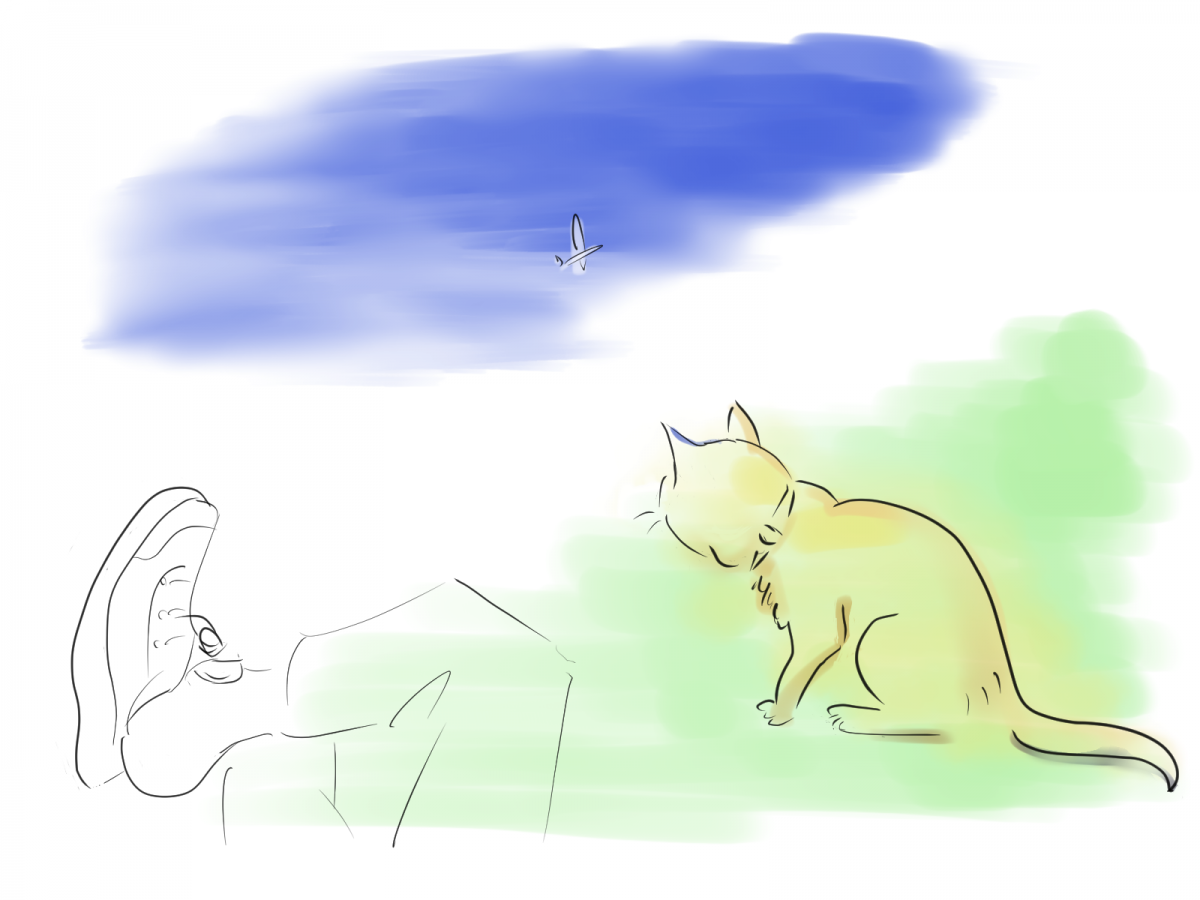最初は気付かなかった。塵のように小さな点が銀色に、木漏れ日がちらつくように見えた。利根川の河川敷まで十キロ程もあろうか。遠く冴えない青空の奥に、グライダーの翼が一瞬陽光を反射した。その閃光は三秒とは持続せず、また薄青色の空に吸い込まれていった。目を凝らしても見えない、静かな平面的な空に完全に沈んでしまう。視野に巨大な大腸菌のプレパラートが浮かんだ。それは細胞膜だけが白く半透明にきらめき、細胞質は青く溶け、ここからは見えない海の色に同化していた。それがグライダーの翼の残像なのかどうかわからなかった。それにしては巨大すぎる気がした。気温三十六、七度か、この今という出来事の底を泳ぐように生きている。それは過去でしかありえない今という自分の檻の中だったのだろうか。そしていつか人は過去を置いていくのか。そして今を持ち去る。どこへ? どこ、という問い自体が成立しない場所へ‥‥いや、むしろ今がかつて一度でもあったのだろうか。汗に湿ったTシャツが背中にはりついている。彼方に銀色の鱗が光った。目の前にあるのは、いつも今という過去でしかない。この今が過去であるがゆえに愛おしかった。いつか置いていくのだろう、そう思った。
小型の重機が林の端に見え隠れする。水田に囲まれた島のような林は、下草が鬱蒼と生い茂り、緑の塊りが空に向かって入道雲のように盛り上がっていた。カボさんの家の取壊しなのだろうか、と思った。狭い未舗装の町道が続いていた。そこは秋になると砂利の上に三千恒河沙の樫の実が展開し、葉擦れの音が響くのだった。椎の木立の向こうに雲が風に流され崩れていった。竹藪に囲まれた巣のような掘立小屋の柱がひしげる音。何年も前から壁が半ば崩落したままの納屋もあった。その薄汚れた埃の中に、安物の食卓用の椅子が置かれているのを見たことがあった。日が翳り、梢の色が濃くなっても、その場所には永遠に陽が射しているような気がした。誰かに、また自らに親密な距離でありたいと願い、その感情に襞を作り、そして亡霊のようにその場所を残していく。死の中に生活が浮かんでいるのだとすれば、生活の中にそれは何喰わぬ顔で滲んでいるのだろう。
自分固有の塊りなどどこにもない。ただ一人分切り分けているにすぎない。だからこそ自らをなぞろうとする。そこから剝ぎ取るのではない。そこには無いのだから。この、何度もなぞられたものである生を、自らの外に重ねていく。この場所に立ちつづけるための意味を読み込もうと、またもう一つの言葉を捜す。
西の空には絹雲が筋を引き、黄と橙と紫の虹がその場所だけ微かに浮き上がっていた。ドリンクゼリーの空袋をごみ箱に投げ捨て、自転車のハンドルを握った。股関節の辺りに違和感があるためペダルが重かったが、半ば蹌踉けながらも僅かに風を起こしていく。爽やかでありたいと願った。タイヤの空気がかなり抜けているせいで、資材置き場の出入口のレールの上を越えるときにガツンと嫌な震動が伝わってきた。穏やかであろうとした。「どうですか、お尻の辺りがポカポカしてきた感じがしますか」という麻酔科の医師の声を思い出した。針生検の施術中、オペ室に流すBGMをリクエストできるのだと予め看護師から説明があったのだが、その時は緊張のあまり忘れていた。じゃあ、ビートルズを‥‥、と例えばアクロス・ザ・ユニヴァースあたりの大人しい曲をイメージしていたから、腰の辺りの背骨に針を刺されながら、とうとうこの時だと観念した瞬間やっと、「ポカポカしてきた感じがしますか」という声の後ろで響いているノイズの効いたギターの単調なフレーズがコールド・ターキーだと気付いたのだった。「アァ‥‥アァ‥‥アーッ‥‥アァーッ!」という麻薬中毒者を模したサイケな狂気の叫びが、下半身をむき出しで仰向けている俺に妙に似合ってはいるが、どこか不謹慎でもあるなと感じた。そうだ、癌細胞が見つかりでもしたら、十二弦ギターを買おう。深みがあって、しかも爽やかな音色はシタールみたいなんだろうな、と想像してみた。
事務所の前に自転車を置くと、昼の休憩時間の終了のベルが鳴り響いた。冷水機で水を飲んでいたシゲさんに、「今日は、なんかムシムシするねぇ」と声をかけると、手の甲で口を拭いながら、「うゥん」という相づちと「ふゥー」という溜息の合いの子のような、少し間の抜けた感じの声をもらして振り返った。シゲさんはいまだに独身だった。酒が入るとしつこくなったが、暗いしつこさではなかった。そんなとき、よく「男は芸者じゃなくちゃ」と、小指を半分ほど立てるのだが、そっちのケがある風でもなく、その言葉の真意は不明なのだった。シゲさんの家は道路を挟んで斜め向かいにあった。それほど広い敷地ではないが、母屋の東側の庭木やちょっとした畑をいじるのが、競艇に次ぐシゲさんの第二の娯楽だ。偶に畑でとれた昔風の小玉西瓜を持ってきてくれた。他の従業員もその殆どが自転車で通える範囲内に住む、いわば近所のおじちゃん、おばちゃんたちだった。
「あ、そうだ。ビニール板、頼んどいてくれ」トラックのキーを渡しながら、シゲさんが言った。
「もう駄目んなっちゃったん? こないだ取っ替えたべえじゃなかったっけ。まだいくらも経ってなかんべで」
「駄目。反っけっちゃってんだから」
「ひっくり返してやってみたん? もう一回ひっくり返してやってんべよ」そう言って、裁断機の所までついて行き、ビニール板を持ち上げる。「駄目だよ、どうせ」と言いながら反対側を支えるシゲさんに、「ま、もうちょっと、これでやってみて……」と、口許で笑う。一枚一万二千円だぞ、と思った。ワンショット二十三円そこそこにしかならない仕事だ。
裁断機の脇の窓からもカボさんの林が見えた。カボさんの林といっても、土地の所有権は何やらややこしく、この辺の大農家は子供らが皆都会に出てしまった家が何軒かあり、この地元の人間でその土地を管理し固定資産税も払っているという人の話として噂で聞いたところによると、所有権を持っているのはそうした元地主の一族で今は神戸や東京に暮らし地元との繫がりもなくなっている者数名だということで、結局カボさん自身の土地でも林でも全然なかったらしいが。二十メートル近くあろう樫の巨木と密林のように群生する灌木や笹、竹に蔽われて、ここからはカボさんのなくなりつつある家は見えなかった。まだ作付けされていない畑側の境界に沿ったところだけ、日に焼けたように茶色くなっていた。褐色の体軀の天辺に陽を浴び、背高泡立草がすっくと立っていた。除草剤の効力に抗うように死んだまま屹立していた。左の窓からは、真白な高い壁に切妻の屋根、小さな窓がいくつか開いていなければ随分立派な蔵だなと間違えそうな造りの二階建ての家が見えた。ここから見えるのは建物の裏だが、三、四メートルのくねの上に覗く換気窓は、夏の間毎日開け閉めされていた。主人を数年前に亡くした老婆が一人で住んでいて、あそこの窓を開けに階段を上るのだ。脚もだいぶ弱っているから、その昇り降りも楽ではないはずだが。双子の兄弟のうち、弟は早くに結婚し、相手が一人娘、跡取り娘だったため、そちらの家に入った。双子の兄、彼女の長男が建てた家、間取りから壁や屋根の形や色までその息子が決めて造った家に、今は一人で暮らしていた。幼い頃、その兄弟と用水路で田螺を獲った記憶がある。夏休みにはよく一緒に遊んだ。新築の住宅に暮らし始めてさほど経たないうちに、彼は入浴中に倒れた。家人が発見したのは翌朝だった。稲穂の淡い緑が目を刺すように毛羽立っていた。今という場所に過去が吹き溜まる。そしてパッとその場所が消え去る。吹き溜まった過去が落ち葉のように残り、もうない場所を示す。そこにはぽっかり穴が開いているのだと。そこには今がない場所がぽっかり穴を開けている。
ブレーカーのレバーを上げ、電源スイッチを捻ると、デジタルカウンタが3、2、1と左から順に点燈した後、635を表示した。ふと欠伸が出た。僅かに涙が滲み、やがて鼻の天辺の裏側の窪みが湿り気を帯びた。その感覚はいつも俺を苛立たせるものだった。眠いことと眠りたいこととは全く別のことだし、この二つのことの間には一つも共通する部分はなかった。もちろん、今眠りたいとは思わないし、昨夜は例のごとく眠りたかったが眠くはならなかった。入眠剤を飲んでも暫く輾転反側しなければならなかった。一時間程すると漸く四肢の末端から痺れが上ってくるのだった。四肢の末端から痺れが上ってくるのを、意識している。つまり、いつもそこで掛け違えが生じている。「眠れないことに拘泥るんですね‥‥あ、いや、眠ることに拘泥るんですね」その言い直しが可笑しかった。だが、眠ることに拘泥らないで何に拘泥るのか、と感じる。掛け違えだけが明らかな気がして、糸のもつれを解きほぐせないまま、覚醒が覚醒であるために是非とも必要な眠りが手に入らなかった。「大きなカテゴリーでいうと鬱病ですね」と、精神科医が言った。鬱病という余りに在りきたりの病名を宣告された一抹の不服感を察知したのか、「まあ、えー、○×△症と言っても良いんですが‥‥」この「○×△症」の部分がそのとき記憶できなかった。「えー」のところで手許の医学書をぺらぺらっとやったが、それがポケット版の全然箔のないやつで、ぺらぺらっと頁を繰る手付も如何にもいい加減なかんじで、形だけというか‥‥、その仕種に気を取られたせいだろうか。四肢から内側へと滲んでくる痺れ、それが物のような身体の、自らによる睡眠へと誘う化学物質の分泌なのだと言いきかせながら、眠りに落ちた。
鼻の裏の窪みの不快感を解決しなければならなかった。ティッシュペーパーを取り、コの字形に曲げた小指の先で鼻の屋根裏に捩じ込んで吸湿する。目を瞑り、目頭に力を込める。小さな金色の滓が一片瞼の裏を飛んだ。角膜のざらつきは諦めるしかなかった。刃型を固定した裁断機の上板が再生フェルトを圧し潰す度に、端面から粉のように細かく千切れる繊維の埃が舞い上がる。眼球表面の乾燥と、繊維に微量含まれるホルマリンも若干影響あってか、角膜が炎症を起こしているのかもしれない。眼鏡では効果がなく、ゴーグルは鬱陶しかった。十二キロほどのロール原反を担ぐ作業は大した肉体労働ではないが、油断していると時には腰を痛めた。五本の原反に鉄製のパイプを通して支柱に掛け、延反した端を送りローラーの下まで引く。あとは機械が自動で裁断する仕組みだ。肉体労働や機械相手の単純労働を敢て好む者は少ないだろうが、そこに俺は安心を得ていた。恕されているという自慰の安直さは、かつて一時期大学の授業にも工場のネーム入りの作業服を上衣代わりに着て行っていた如きだった。もちろん、ジャケットを持っていなかったことも一方ではあったのだが。もはや現実としては階級闘争の主体というのは幻想だろう。高校生の頃、何かの小説を読んでいた折に、「苦力」(coolie)という単語に出会ったときゾクッときたのを思い出す。つまり、「苦」な仕事であり、それを生業とする人間は、人間としてより労働「力」として把握されている。いや、そんな理屈よりも、「苦力」という単語から膨らんだイメージが、この世界全体に決定的に色付けし、その色は或る真理を含んでいると感じたのだ。ここからもう一つの幻想が妄想として、より魅力を帯びてきたのは間違いなかった。自動送りローラーが押し出す型打ちされた再生フェルトから製品を抜き取り、残った抜き代を千切る。軍手をした指先に感じる存在の確かさは、妄想の核であり自慰の虚しい担保だった。しかし、資本の搾取の片棒を担ぎつつ自らも搾取されるパン職人の親方は工場労働者よりもずっと惨めだという。働きに来てくれている九人のパート従業員の人達は十万円そこそこしか受け取れないのだ。手の労働が担保する存在の明証などなかった。今という幻を購うために、機械のリズムに同化した。もどかしさと怯えに満ちた贖罪じみた棘から免れようと、過去も未来もないこの場所に、湧き出る瞬間に消え去るこのリズムに同化しようとした。製品を鉄製のテーブルの上で叩きポンチ屑を払い落す動作が、どこかパーカッショニストに似ていると思った。リズムが疲労感を確実に和らげた。
何も始まらない、何も終わらないように見えるこの場所にこそ、何かが突出してきているような気がした。もう何千日こうやって毎日同じような作業を繰り返しているだろう。毎日同じようなことを考え、同じような感情に浸っているのも確かだが、また一方で必ず新たな想念が二つや三つ浮かび、ささやかながら気持が襞をおっていく。それが毎日何千日も続いてきたのだ。
(つづく)